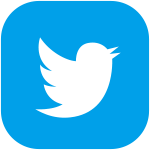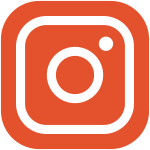議会質疑
PARLIAMENTARY QUESTION
厚生委員会
2024年11月27日 令和6年厚生委員会
山加朱美
冒頭、委員長から、各議員が手短に要領よくというご要請がございましたので、しっかりと頑張らせていただきたいと思います。
また、重複するテーマもございますけれども、角度を変えて質問をさせていただきたいと思いますので、理事者の皆様におかれましては、内容の濃い答弁をひとつよろしくお願い申し上げます。
まず、二〇一二年、障害者手帳の有無にかかわらず、社会参加、真の共生社会に資するマークが必要ということで、私の体験から、このヘルプマークを提案させていただきました。
当時、石原都政がこの提案を受けて実現をいただいたわけでありますが、所管局の福祉局はどちらかというと、前例がなかったということで、ちょっと後ろ向きな印象を持っておりますけれども、ただ、二〇一七年、日本の新しい福祉のマーク、JISに採用されまして、そして、観光地の京都が最初に飛び火をしたと思いますが、そこから全国に飛び火をいたしまして、もちろん以降は、所管局、福祉局の担当者の皆さんも全力で力を注いでくださったおかげでございますけれども、ただ市民力が、やはり大きく作用したと確信をいたしております。
現在では、四十七都道府県全てで導入をされ、新しい日本の福祉のマークとして、社会参加するのに必要な皆様の不安を取り除いてくれているなと感じるところであります。
この時期になりますと、中学生、高校生、大学生から、恐らく卒業の論文であったり、研究テーマであったりすると思うんですが、私の方には、ヘルプマークの提案者として意見を聞かせてほしいというお電話やメールが結構たくさんいらっしゃいます。
数年前にも、中学生の方が提案者の声を聞きたいということで、都庁にお越しになられました。三年たって、今、高校生になって、自分たちが、ヘルプマークのことは分かったけれども、じゃあ、自分たちに何ができるんだろうと考えて、ポスターがつくりたい、ただ、ヘルプマークは東京都が商標登録を持っていますから、どうやって許可を取るんですかというお問合せでいらっしゃって、ポスターをおつくりになって、校内に貼るポスターですから、こんなのができましたって送られてきました。あっ、このマーク見たことある、知っているだけじゃ何も変わらない、まさにそのとおりであります。
現在、日本のマークとなりましたけれども、まだまだ知らない、見たことはあるけれども、知らないという方も多いなと感じております。
今年の春、国会でも超党派で、このヘルプマークの推進に力を注いでいこうという議員連盟が立ち上がりまして、その設立総会に、ヘルプマークの提案者としてちょっと経緯とお話を伺いたいとご要請がありましたので、伺ってまいりました。やはり、マークは知っているけれども、深い意味まではもう一歩という先生方もいらっしゃいました。都民の皆様では、なおさらのことと思いますので、ぜひ、発祥の地の東京都として、日本のマークとなりましたけれども、これからも力を入れていただきたいなと思うところであります。
まず、ヘルプマークに関してお伺いいたします。
確認の意味で、都は、ヘルプマーク作成の初年度、どのくらい作成し、今年度はどのくらい作成予定でしょうか。併せて、これまでの配布状況、配布場所について、改めて伺います。
加藤障害者施策推進部長
都は、ヘルプマークを作成初年度でございます平成二十四年度に六万五千個作成いたしまして、今年度は七万八千個を作成する予定でございます。
ヘルプマークは、都営地下鉄各駅、都営バス各営業所、東京都心身障害者福祉センター、都立病院等で配布をしておりまして、令和六年三月末までの累計で約六十二万一千個を配布しております。
また、区市町村において作成をし配布する場合には、包括補助事業で支援をしております。
山加朱美
令和五年三月時点の都内の障害者手帳の所持者数は約七十四万人ですが、手帳の所持にかかわらず、このヘルプマークを真に必要としている方、社会参加するに当たり配慮の必要な方の数は、もっとたくさんいらっしゃると思います。
ヘルプマークを必要とする方が、ご自身が必要と感じたときにすぐに入手できる、東京はもらえる場所が多いですから非常に便利だと思っておりますが、ただ、地域を回りまして、私の練馬区、有権者から、先生、このマークもらいに行ったら在庫がないっていわれたよ。いや、そんなはずはないなと思いまして、都営交通の改札、事務所でもらうことができますので、練馬区は光が丘に福祉事務所がありますので、もらいに行く方も多いと思いますので、実は私ももらいに行きました。聞くだけでなく、自分自身も体験しないと分かりませんので、そうしましたら、やはり在庫ありませんといわれてしまいました。
ぜひ、ヘルプマークを本当に必要としている方、援助、配慮が必要な方、困るような状況を発生させてはならないと思います。
そこで、交通局との連携状況、在庫切れにならないための取組について伺います。
加藤障害者施策推進部長
昨年度実施をいたしましたインターネット都政モニターアンケートによりますと、ヘルプマークについて、意味も含めて知っていた人は六六・五%でございまして、ヘルプマークを希望される方も増えております。
これまでも、最寄り駅等、身近な場所で希望者が確実に入手できるよう、交通局と随時在庫状況の確認等をしてまいりましたが、今後は、ヘルプマークの在庫管理を徹底いたしますとともに、定期的に連絡を行うなど適切に連携を図ってまいります。
山加朱美
来年度は聴覚障害のデフリンピックが東京で初めて開催をされるわけであります。実は私も聴力が六十デシベル、難聴の一歩手前まで聴力を落としまして補聴器を使用しておりますが、補聴器を離しますと、もうほとんど音が取れません。自分の声もよく取れないんですけれども、ある日突然というのは誰にでもあり得ることであります。
私自身、このヘルプマークを提案したのは、事故により人工股関節を挿入、その後、一か所の機能欠損を抱えますと、どうしてもよくて現状維持、悪ければどんどん機能の低下があります。今年、残念ながら膝も人工関節、自分の機能を全廃いたしまして、やっとつえが取れて、自力で、ただ、リハビリはまだ進んでおりません。
様々な機能欠損、また、障害の有無にかかわらず、社会参加は皆様の本当に温かな支えがあってできるなと思っております。ぜひとも、このデフリンピック、内外から多くの、障害、不自由さを抱えた、そのことが分かりにくい方が日本にいらっしゃると思いますので、引き続き、この配慮のマーク、ヘルプマークのさらなる取組に期待を申し上げたいと思います。
次に、車椅子使用者と駐車区画についてですが、バリアフリー法による整備が進められている、皆様ご存じの国際標準化、車椅子使用者の駐車区画は、車椅子を使用している人も乗り降りしやすいよう、三・五メートル以上の幅が必要とされまして、建物の出入口、エレベーターホールなどに近い場所に設けられております。私は、かねてより、この車椅子使用者等の利用する障害者の駐車区画、ここは障害者手帳を有していなければ止めることができませんので、そこに必要としない方が止めてしまうことによって、本当に必要な人が止めることができない、規範意識の薄さに、これまでも問題視をして提言をしてまいりました。
この車椅子使用者の障害者駐車区画のほかに、高齢者、妊婦さん、車椅子を使用しないけれども歩行に困難を抱えて長い距離の移動に配慮が必要な人を対象とした優先駐車区画があります。ここは三・五メートル以上の幅を必要とせず、このヘルプマークを使用している方も利用しやすい駐車区画でありますが、この優先駐車区画を増やしていく必要があるということで、昨年、提案をさせていただきました。
来年のデフリンピック開催を見据えまして、駐車区画の適正利用に向けた取組についてお伺いしたいと思います。優先駐車区画の設置を促進するため、まず、これまでどのように取組を進めてきたのか伺います。
渋谷事業調整担当部長
都は、車椅子使用者等の駐車区画とは別に、通常の区画を活用し、車椅子使用者ほど広いスペースを必要としない、歩行に配慮が必要な方が利用できるよう、優先駐車区画の設置を望ましい整備基準として、福祉のまちづくり条例のマニュアルに記載しております。
令和五年度には、障害者や高齢者、妊産婦など、移動に配慮が必要な方が利用できる駐車区画である優先駐車区画の設置を促進し、車椅子使用者等の駐車区画は車椅子使用者の方が適切に利用できることが重要であると考えまして、ヘルプマーク等を明示しました優先駐車区画用の標識を作成し、区市町村へサンプルを配布いたしました。
山加朱美
確認の意味で伺いました。
昨年、提案させていただきましたが、令和五年度に作成をいただいたヘルプマークを明示した優先駐車区画、この標識であります。これですね、現物。カラーコーンにこれをかぶせるようになっていまして、ヘルプマークを入れ込み、障害者手帳は持っていないけれども、社会参加する上で車が必要で、やはり現地に行かなければ──場所がなければ止めることはできませんが、障害者手帳がなくても優先的に利用できる、大変分かりやすいデザインとなりました。
ヘルプマークを所有している方などが社会参加するに当たり、利用しやすいこの優先駐車区画、これを拡充するために、大変有効なものと思いますが、外出するに当たっては移動に不安を抱えている都民の皆様が安心して社会参加する上でも、真の共生社会のさらなる推進のためにも有効であると思っています。
昨年度に続き、今年度も追加で配布するなど、取組の充実が必要と思いますが、ヘルプマーク等を明示したこの優先駐車区画の標識について、まず、区市町村へどのように配布をしたのか伺います。
渋谷事業調整担当部長
令和六年三月に、区市町村連絡会において優先駐車区画用の標識の活用について周知を行った上で、区市に各二枚、町村に各一枚を配布するとともに、区市町村が標識を作成するための印刷データを公開しております。
また、区市町村が優先駐車区画用の標識を作成する場合、その経費につきましては包括補助で支援しております。
今後、区市町村の公共施設を中心に、優先駐車区画の設置をさらに促進していただくため、年度内に区市に二十枚、町村に十枚の標識を追加で配布する予定でございます。
引き続き、区市町村の公共施設における優先駐車区画の拡充に向け、積極的に働きかけてまいります。
山加朱美
区市町村への取組については分かりましたが、区市町村における優先駐車区画の拡充の取組を進めていくためには、まず、都が範を示す必要があると思います。
都の施設にはどのように配布をしたのでしょうか。
渋谷事業調整担当部長
これまで、都の各施設におきましても、優先駐車区画の設置に取り組むことができるよう、まずは移動に配慮が必要な方の利用が多いと見込まれる都立病院、保健所等に約四十枚の標識を配布いたしました。
今年度は、さらに庁内各局における取組を進めるため、各局へ優先駐車区画用の標識の必要数を調査いたしまして、これを基に、年度内に合計三百二十枚程度の標識を追加で配布する予定でございます。
引き続き、庁内各局に対しましても、優先駐車区画の意義を説明した上で、都の施設における優先駐車区画の設置促進に取り組んでまいります。
山加朱美
数ある都の施設に対して、今、合計三百六十枚程度の配布ということでしたが、これで十分といえるのかなと、はてなマーク、私はまだまだ足りないと思います。
また、先ほど区市には、三月にサンプルとして二枚、さらに年度内に追加二十枚、合わせて二十二枚ですね。町村には、三月にサンプルで一枚、その後追加で十枚、つまり十一枚ということですが、私も、まだ、ほどんどこれを拝見したことがあまりございません。ゼロの数をちょっと聞き間違えたかなと思うくらいなんでありますが、ちょっと厳しく申し上げますと、やはり一層の拡充が必要と考えます。
車椅子使用者等の障害者駐車区画の適正利用をさらに進めるためにも、都がさらなるリーダーシップを発揮していくことが必要です。さらには、新たにこの提案を受けて都がつくってくださった優先駐車区画の標識を使って、区市町村の公共施設における優先駐車区画を一層拡充させていただきたいと思います。
ぜひ、この配布枚数を、区市に二十枚、町村十枚ということではなくて、それでは区役所や市役所にしか置けないと思うんです。ぜひとも、その枚数を増やしていただき、そして、十分に都民の理解が得られるように、真の共生社会の実現に向けて、皆様のご努力をお願い申し上げたいと思います。
次に、テーマは重なりますが、重症心身障害児者の支援についてお伺いいたします。これ、ちょっと私の練馬区とも関わりありますので、お伺いします。
重度の肢体不自由と重度の知的障害を重複する重症心身障害児者は、都内に約四千人以上おられます。こうした方々の多くは在宅で生活をしていらっしゃり、また、気管切開を行ったり、人工呼吸器を装着するなど、医療的なケアが欠かせない方が多く、ご家族は大変な苦労をなさっていらっしゃいます。
こうした重度の障害を持った方、医療的なケアが必要な方に対し、様々な施策の取組をされていると思いますが、都は、改めて、これまで在宅で暮らす重症心身障害児者の方の支援にどのように取り取り組んできたのかお伺いいたします。
加藤障害者施策推進部長
都は、東京都障害者・障害児施策推進計画に基づきまして、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら障害児者やその家族が地域で安心して暮らせるよう、日中活動の場である通所施設の整備を促進いたしますとともに、一時的に家庭での療育が困難になった場合に、施設等に短期間入所できる病床を確保するなど、在宅支援サービスの充実に取り組んでおります。
令和六年三月末現在、重症心身障害児者を受け入れることのできる通所事業の定員を九百六十二人分、また、重症心身障害児者を受け入れることのできる短期入所を令和六年四月一日現在、百五十三床確保いたしまして、重症心身障害児者の在宅生活を支援しております。
山加朱美
重症心身障害児者が地域の中で暮らせるための様々なサービスを充実されていることは、高く評価をしたいと思います。
こうした中で、私の地元練馬区では、このたび区有地を事業者に無償で貸付けをし、五十年の無償貸付ですね、医療的ケアにも対応した重度障害児の地域生活支援拠点を整備するという計画を、先月公表いたしました。在宅生活を支える機能として、都の施策とも合致をしています。
そこで、こういった施設の整備に対して、都としてどのような支援があるのか伺います。
加藤障害者施策推進部長
都は、重症心身障害児者の在宅での生活を支えるため、日中活動の場である通所施設の整備費や運営費に対する都独自の補助を行っております。また、病院のほか、医療機能を有する福祉施設などを対象といたしまして、人員配置や医療機器の整備への支援を行い、重症心身障害児者に対応できる短期入所の拡充を図っております。
今後とも、区市町村と連携しながら、こうした取組を進め、重症心身障害児者とその家族を支援してまいります。
山加朱美
ぜひとも、区市町村としっかりと連携をして進めていただきたいと思います。
今月は十一月。皆様もオレンジリボンをつけていらっしゃる、当然ですけれども、東京都の児童虐待防止推進月間であります。私も、このオレンジリボンは三百六十五日つけて啓発をさせていただいております。
最後に、児童虐待対応についてお伺いをしたいと思います。
都内の児童虐待相談対応件数は、いまだ増加の一途をたどり、悲しいばかりであります。令和四年度二万六千百二十三件でした。児童相談所が受けた相談のうち、子供の生命の安全を確保する必要がある場合には一時保護し、里親委託、施設入所につなげています。また、地域において関係機関と連携しながら、親子に対して援助することが適当と判断された場合は、在宅での支援が行われています。
虐待相談対応件数が増え続ける中、深刻な虐待から子供の命を着実にしっかりと守りつつ、地域において子育て家庭をしっかりと支援していくためには、児童相談所の体制強化、子供家庭支援センターとの連携の強化が必要であります。都の取組を伺います。
西尾子供・子育て支援部長
児童虐待の対応につきましては、児童相談所は法的対応や専門的な相談支援を担っており、子供家庭支援センターは地域の第一義的な相談窓口として、子育て支援サービスなども活用しながら児童や保護者からの相談支援を行っております。
このおのおのの役割を踏まえまして、虐待対応における連携、協働のための東京ルールに基づき、両者が緊密に連携しながら児童と家庭を支援しております。
また、児童相談所の体制強化につきましては、虐待相談に迅速かつ的確に対応するため、児童福祉司、児童心理司の増員を図っております。
さらに、子供家庭支援センターが地域での支援をきめ細かに行えるよう、虐待対策コーディネーターや児童相談所と連携強化するための職員の増配置を支援しております。
山加朱美
本年九月、こども家庭庁が児童虐待による死亡等の重大事例の検証結果を発表しました。対象となる事例の約半数がゼロ歳児でした。これは大変な衝撃でありました。こうした虐待を防ぐためには、出産、子育てに不安を抱える家庭に対し、妊娠時からの継続的な相談支援の充実を図っていくことが重要であります。
国は、本年四月、区市町村において子供家庭支援センターの設置を努力義務化しました。冒頭、我が党の浜中副委員長からも、このことに関しては質問がございましたけれども、この子供家庭支援センター、児童福祉と母子保健の部門が一体的に相談支援を行う機関であります。
この子供家庭センターにおいて、妊産婦に対して、先ほど副委員長もおっしゃいましたけれども、実効性がある支援を行えるよう、形だけでなく、しっかりと中身をつくっていく、それは当然であります。
都として、区市町村をしっかりと支援をしていくべきと考えますので、さらに詳細な取組をお伺いしたいと思います。
西尾子供・子育て支援部長
都は今年度から、こども家庭センター体制強化事業を開始しておりまして、区市町村の児童相談部門と母子保健部門が一体となって、妊娠期からアウトリーチによる継続的な相談支援を行い、子育て家庭のニーズや困り事を早期に把握し、適切な支援につなげるよう、区市町村を支援しております。
具体的には、保健師や心理職などの専門職に対し、当事者の視点に立った面接技法や、チームアプローチによる支援方法などの実践的な研修を行っており、これまでに三十二自治体が参加をしております。
また、両部門の連携を担うリーダー職員の増配置を支援しており、今後とも区市町村における虐待防止の取組を促進してまいります。
山加朱美
ありがとうございます。
これからの未来を担う全ての子供のかけがえのない命を児童虐待からしっかりと守るため、また、失われなくて済む命をしっかりと守り、支えるために、都としての児童相談体制の充実、子供家庭支援センターとの連携強化に一層取り組んでいく必要があると考えます。ぜひ、局長の強い決意をお伺いさせていただきたいと願います。
これで私の質問を終わります。
山口福祉局長
深刻化、複雑化する児童虐待に的確に対応するためには、都全体の児童相談体制を強化しますとともに、都と子供家庭支援センターをはじめとする地域の関係機関が緊密に連携することが重要でございます。
都は今年度、区立児童相談所や子供家庭支援センターを含めた都全体の児童相談体制を強化するため、児童相談センターに新たに総合連携担当を設置いたしまして、各機関の業務の標準化や個別ケースに係る専門性の向上、協働での人材育成などの取組を行っております。
また、児童福祉司や児童心理司、子供家庭支援センターの専門職などの増配置を進めますほか、人材育成のためのトレーニングセンターを設置しまして、今後、子供家庭支援センターとの合同研修を充実するなど、研修を通じまして顔と顔の見える関係を築いてまいります。
さらに、児童相談所の管轄人口などを考慮し、管轄区域の見直しを進めておりまして、今年度、練馬児童相談所を開設しましたほか、来年度以降、五か所に新設をし、よりきめ細かな相談援助の体制を整備いたします。
今後とも、子供の最善の利益を実現するため、区市町村や関係機関と連携を密にしながら、児童虐待防止に全力で取り組んでまいります。
出典:令和6年厚生委員会 本文 2024-11-27
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/welfare/2003-14.html
戻る