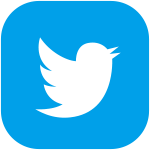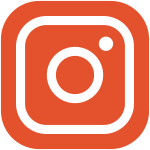議会質疑
PARLIAMENTARY QUESTION
厚生委員会
2024年11月28日 令和6年厚生委員会
山加朱美
私からは、まず広尾病院についてお伺いをしたいと思います。
私、広尾では、十年ほど前に命をつないでいただき、今があることに大変感謝をいたしております。また、広尾は、島しょ医療に大変力を入れてくれておりますので、都民の方にとってはなくてはならない大切な病院であります。移転をするのか改築をするのか、大変な、数年にわたって紆余曲折がありましたが、最終的には現地での建て替えということになりました。
整備事業に関してお伺いをしたいと思います。
この整備事業に係る入札も、昨年一月に、建設資材や労務費の高騰等の影響を受け不調となっています。その後、五月に整備基本計画等を修正の上、再度入札公告を行い、落札者が決定をされました。
現在の広尾病院整備事業について、進捗を伺いたいと思います。あわせて、事業への理解を深めるためには、住民への周知も大変重要でありますので、その取組を伺います。
鈴木都立病院支援部長
広尾病院の整備事業につきましては、都立病院機構におきまして、再度入札公告を行い、今年六月、事業者と契約締結を行いました。現在は、既存の建物につきまして解体のための設計を行っており、来年には、看護専門学校から順次解体工事に着手する予定でございます。
また、今年十月には、住民との意見交換会を実施し、解体工事の工事手法や新病院における建物配置などにつきまして丁寧にお伝えした上で、住民との共通認識を図ったところでございます。なお、島民の方々に向けても、年二回発行している島しょ医療NEWSを活用し、事業の進捗に応じた周知を行うなど、丁寧な対応を行っております。
山加朱美
いよいよ来年から解体工事が始まり、具体の工事が始まってくる中で、工事期間中に病院機能をどのように維持していくのかが重要であります。
令和五年に一部修正した整備基本計画等では、病院機能の維持に当たっては、仮設棟を建設せずに既存の本館改修等により機能を確保することも可能とし、その後の整備内容の詳細については、今後実施する基本設計及び実施設計において定められていくこととされたと認識をいたしておりますが、そこで、現在の病院機能の維持に当たり、仮設棟は、つくることで維持をするのか、それとも既存の本館改修により行うのか、検討状況をお伺いいたします。
鈴木都立病院支援部長
令和五年五月に一部修正した基本計画では、事業者が一層の経費削減や工期短縮のほか、知見を生かした創意工夫のある提案を可能とし、契約締結後は事業者と協議を進め、整備事業が円滑に進められるよう検討を行いました。
病院機能の維持につきましては、既存病院を改修する整備手法においても可能であり、工期も短縮できることから、都立病院におきまして、仮設棟を建設せず既存病院改修により整備事業を進めることといたしました。
そのため、医療提供機能を補助する医局、当直室等については、改修により本館の中で確保し、島しょ患者家族宿泊施設、職員宿舎、院内保育室につきましては、代替施設の確保等により、機能を維持してまいります。
山加朱美
既存病院の改修により病院機能を維持しながら整備事業を進めていくとのことですので、施設整備期間中は、当然、外来機能、病床数等を縮小した形での運用を余儀なくされると思われます。工事期間中であっても必要な医療が確実に提供されなければなりません。
本当に必要な医療を提供されるのか、病院、外来それぞれについてお伺いをいたします。
鈴木都立病院支援部長
入院機能につきましては、工事期間中必要な病床数を確保し、重点医療のほか一般医療につきましても確実に提供してまいります。
外来機能につきましては、現在、診察室の一部がある既存病院別館の解体を令和八年度以降に予定していることから、当面の外来診療はこれまでどおり行いつつ、今後の運用につきましては、患者動向も見据えながら、影響を最小限にとどめられるよう検討を行ってまいります。
工事期間中も広尾病院の限られた医療資源を最大限有効に活用し、地域医療機関等との適切な役割分担と密接な連携を通じまして、地域の医療ニーズに応えてまいります。
山加朱美
地域の医療機関との役割分担と連携の下、地域医療の充実に取り組むことは都立病院の使命であります。整備事業を一つのきっかけといたしまして、これまで以上に地域医療機関との連携を深化させ、新病院開設後も継続していくことをお願いしたいと思います。
そして、島しょ患者家族宿泊施設、職員宿舎、院内保育室についてですが、これらの機能については、先ほど代替施設等の確保により、機能を維持していくとの答弁をいただきましたが、具体的にはどのように機能を維持されるのでしょうか。
鈴木都立病院支援部長
お話のございました施設は、工事期間中、敷地内に確保することが難しいため、代替施設の確保等により機能を維持していくことといたしました。
具体的には、島しょ患者家族宿泊施設につきましては、近隣ホテルの借り上げにより、工事期間中も現在と同様の部屋数を確保するとともに、使用料も現在と同額で利用いただけるよう準備を進めていくほか、職員宿舎につきましては、代替物件の確保により対応いたします。
また、院内保育室につきましては、代替施設を設けるのではなく、職員の理解を得ながら、保育料助成制度の利用に切り替えることで対応してまいります。
山加朱美
広尾病院の島しょ患者家族宿泊施設は、島民の方にとっては非常に重要な施設であります。今ご答弁いただきました、工事期間中は一時的に病院の敷地の外になるわけですが、近隣に、現在と同様の施設料で確保していただけるということで、大変安心をいたしました。
広尾病院は、救急医療、災害医療、島しょ医療などのまさに行政的医療、総合診療など様々な特色ある医療を提供する都民にとっては重要な病院であります。今後とも円滑に整備事業を進めていただくことを期待申し上げます。
次に、臓器移植に関して伺いたいと思います。
臓器移植は、重い病気、事故などにより臓器の機能が低下した方に他者の臓器を移植して機能を回復させる、まさに善意の第三者に支えられている医療であります。
日本では、この臓器移植を希望して待機をしている方が約一万六千人を超えている中で、実際に移植を受けられた方は約六百人となっています。移植件数は、昨年、令和五年は過去最高でありましたが、しかし、それでもアメリカ、ヨーロッパの諸外国と比べれば格段に少なく、現在も臓器移植を待っている方が大勢いらっしゃいます。
件数の増加に伴い、臓器移植のあっせん機関には業務が集中するなど、様々な課題が山積をいたしております。ぜひとも、今後も引き続き、臓器移植対策の推進に向けて、体制整備を行っていく必要がありますので、よろしくお願いを申し上げます。
令和六年、今年の予算特別委員会におきまして、我が党の磯山議員が都における今後の取組について質問をさせていただき、保健医療局長から、本年度、新たに院内ドナーコーディネーターの配置を働きかけるなど、移植医療のさらなる推進に向けて取り組んでいくとご答弁をいただきました。
そこで、今年度から開始する院内ドナーコーディネーターの認定制度の現在の取組状況をお伺いいたします。
小竹保健政策部長
院内ドナーコーディネーターは、勤務する医療機関において、マニュアルの作成や連絡体制を確保するなど、臓器提供に関する院内体制の構築に当たって中心的な役割を担うものでございます。また、実際の臓器提供時には、患者のご家族に対する説明及び院外の関係機関と連絡調整などを行います。
都は本年九月に、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針において高度の医療を行うとされております五つの類型に当てはまる都内全ての医療機関に呼びかけまして、院内ドナーコーディネーターの設置促進に向けた説明会を開催いたしました。
今後、医療機関からの推薦に基づきまして、院内ドナーコーディネーターの認定を行い、定期的に研修会を開催し、スキルアップを図ってまいります。
山加朱美
九月に説明会を行ったということですから、現在設置に向けた取組が進められていることが分かりました。臓器移植の推進に重要な役割を果たす院内ドナーコーディネーターの設置は、院内の体制整備、さらには、都内における移植医療の円滑な実施につながるため、大変重要であります。今後とも、都内の臓器移植体制の整備がしっかりと進むように取り組んでいってほしいと思います。
一方、そうした体制整備に加え、都民への普及啓発、これも大変重要であります。臓器提供の意思表示について考えるきっかけとして、継続的に実施していくことが大変必要であると考えます。
そこで、都における臓器移植に関する普及啓発の取組をお伺いいたします。
小竹保健政策部長
都では、意思表示に関する普及啓発活動を実施しており、区市町村を通じてリーフレットを配布するとともに、毎年十月の臓器移植普及推進月間を中心に、SNSを活用した啓発や東京腎臓病協議会との共催で、都立公園にて、臓器提供意思表示カードを配布するイベントなどを実施しております。
さらに、今年度は、都民の方のより一層の理解を促進するため、初めて都庁舎や隅田川橋梁のライトアップを実施したところでございます。
今後も引き続き、普及啓発活動を実施するとともに、都内の移植医療の推進に向け取り組んでまいります。
山加朱美
体制整備のほか、都民の意識醸成に向けた普及啓発においても、従来の取組に加えて、新たに都庁舎のライトアップを実施するなど、大変工夫をして行っていることを確認いたしました。
日本は医療技術が大変高いこともあり、今後、移植医療の体制整備が一層進めば、待機期間の短縮などにより移植を受けられる方がさらに増えていくのではないかと考えます。
近年、臓器移植については様々な報道がされていますが、今後とも、提供体制の整備、普及啓発の実施など、都としての臓器移植の取組を確実に進めていってほしいとお願いいたします。
次に、感染症対策に関してお伺いをいたします。
近年、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大をし、未知の感染症が発生した場合には、時を置かずして瞬時に世界中に拡散し、パンデミックを起こしてしまいます。これまで、SARS、重症急性呼吸器症候群、また、ジカウイルス感染症の感染拡大が発生をし、さらに、記憶に新しい二〇二〇年以降、新型コロナが世界的な大流行を引き起こす等、新興感染症は今や国際的な脅威となっております。
感染症はいつ病原体が侵入をするのか予見できませんし、さらに、一旦侵入すれば急速かつ広範囲に拡大をし、都民の健康と安全にとって大変大きな脅威となることは明白であります。
次なる感染症危機の際、迅速に対応できるよう、平時から医療提供体制を強化していくことは重要であります。都の取組についてお伺いをいたします。
小原感染症対策調整担当部長
都は、本年三月に改定した感染症予防計画におきまして、新興感染症発生時の確保病床や発熱外来等の数値目標を設定いたしますとともに、感染症有事の際に機動的かつ的確に対応できるよう、医療機関と病床確保や発熱外来等の感染症対応に係る協定締結を進めております。
今年度は、新たに協定締結医療機関に対し、感染症発生時に備えた体制整備に資するよう施設、設備整備の補助を行うほか、東京都医師会など関係機関と連携し、感染症対応に必要な知識や技術を習得するための研修を実施いたしております。
山加朱美
協定締結、また人材育成等を通じて、それぞれの医療機関が平時から備えておくことは非常に大切な点であり、引き続き取り組んでいただきたいと思います。
一方で、新型コロナのような今回のパンデミックに対しては、都が広域的な視点から、都内の医療資源、感染状況を俯瞰し、区市町村の域を超えた対策を実施していくことが重要であります。関係機関同士が顔の見える関係性を構築し、日頃から連携を深めておく必要があります。
関係機関の連携を強化し、都が広域的な視点から感染症対策を講じていくべきと考えますが、どのような取組を行っているのか伺います。
内藤感染症対策部長
新型コロナでの対応におきまして、地域を超えて急速に広がる感染症に対して、関係機関が緊密に連携し、広域的な視点から対応していくことの重要性が改めて明らかとなりました。
都は、感染症予防計画において、保健所設置区市や感染症指定医療機関等が参画する東京都感染症対策連携協議会を通じて、平時から連携体制の強化を図ることとしております。今年度は、六月に保健所連絡調整部会、七月に予防計画協議部会をそれぞれ開催し、医療措置協定の締結状況や研修、訓練等について、関係機関と共有を行っております。
新興感染症発生時には、平時に築いた連携体制を生かしながら、広域的な入院調整、保健所体制の支援など、都による総合調整の下、統一的かつ機動的な感染症対策を行ってまいります。
山加朱美
協定を締結した医療機関に対し、研修、設備整備支援を実施するとともに、協議会を通じて関係機関との連携を図っているということでありますから、ぜひとも、次なる感染症への対応としては、平時からの備えが欠けることがあってはなりません。今後ともコロナ対応の知見、経験を生かし、関係機関との連携の下、有事への備えを着実に進めていってほしいと思います。
実は、私は二十年前、二〇〇四年、SARSのときに、動物由来新興感染症が世界的なパンデミックを引き起こす可能性がある、そのことを当時の石原知事に一般質問で問うたことがあります。そのとき、知事も関係機関としっかりと連携を取り備えていく、日頃からの備えが必要であるということをご答弁いただいたと記憶をいたしております。
そのときからの、関係機関の皆様方が懸命なご努力をいただいたおかげで、今回のコロナのパンデミック、大変なことでありましたが、ふだんからの備えがしっかりと生かされた、その結果だと私は高く評価をいたしております。
今後とも、次なる感染症に対して、ぜひとも努力を惜しまず、精進をいただきたいとお願いを申し上げます。
次に、災害医療に関してお伺いいたします。
本年一月発生した能登半島地震では、十月末時点で死者四百十二名、うち災害関連死亡百八十五名、家屋倒壊六千四百二十五棟に上っています。被災地の医療を継続するために、全国から多くの医療チームが応援に入りました。とりわけ、DMAT、災害派遣医療チームは、地震発生から一か月の間で延べ約一千隊を超えるチームが被災地で医療支援活動に従事し、活動してくれました。心から敬意を表したいと思います。
さて、都が令和四年に公表した首都直下地震の被害想定では、都内で最大規模の被害が想定される都心南部直下地震で、死者は六千人以上、負傷者は九万人以上となっています。さらに、被害想定では、医師や看護師などの医療従事者が被災した場合、病院での負傷者の受入れが困難となる可能性が指摘をされています。こうした状況下、都内の医療を継続していくためには、全国からの医療チームの応援が必要不可欠であります。
そこで、首都直下地震において、全国から応援に駆けつけてくださる医療チームを受け入れるに当たり、都はどのような取組を行っているのかお伺いをしたいと思います。
新倉医療政策部長
首都直下地震発生時に、負傷者の治療をはじめ、被災者へ医療を提供していくためには、全国から応援に来る医療チームを円滑に受け入れ、効果的に活動してもらうための体制を整備しておくことが重要でございます。
都はこれまで、災害時医療救護活動ガイドライン等において、応援医療チームの参集場所や活動内容など、応援の受入れ体制を定めるとともに、訓練などを通じて必要な見直しを行ってまいりました。
本年九月には国と合同で、首都直下地震を想定した大規模な実動訓練を実施し、全国から百十九チーム、四百七十五名のDMAT隊員が実際に都内に参集して、都庁本部や災害拠点病院等において活動を行いました。
今回の訓練については、年内に検証を行って課題を洗い出し、都の災害医療協議会等で具体的な改善策を検討して、受入れ体制のさらなる充実強化を図ってまいります。
山加朱美
具体的に詳細な答弁をいただき、ありがとうございました。
私はかねてより、未曽有の災害に対しては、過去の体験から常に教訓を得て対策を見直し、災害への備えを万全にして対応策をあらかじめ講じておくことが、行政に最も期待されていることであると指摘をしてまいりました。
首都直下地震を含め、いかなる災害が生じようとも、都民が不安を感じることなく、しっかりと医療が継続されるよう、今後とも引き続き、国や全国の自治体とも連携をし、取組を進めていってほしいと強くお願いを申し上げ、私の質問を終わります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
出典:令和6年厚生委員会 本文 2024-11-28
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/welfare/2003-14.html
戻る